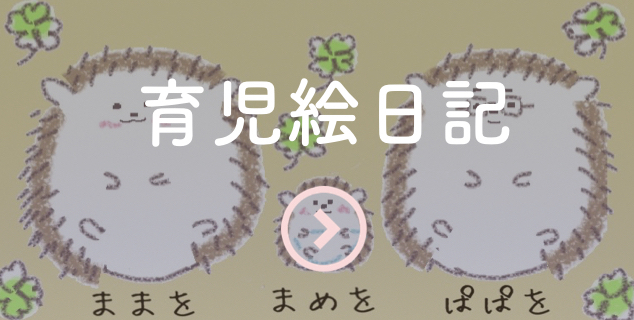どうも、ぱぱをです。
この度ようやく確定申告で医療費控除の申請をしたので、そのやり方を共有しておきたいと思います。
出産した年は、医療費控除で所得税として収めたお金が一部戻ってくる可能性が高いので、診療を受けた際の診療費と薬剤費の領収書を一枚残らずとっておきましょう。
医療費控除とは
申告する人やその人と生計を一にする配偶者、その他の親族のために、支払った一年分の医療費が、一定額を超える場合は超えた分を所得金額から減額してもらえる制度です。
簡単に言うと、その年の医療費がたくさんかかったら、その分税金を返してあげるよ、というちょっとうれしい制度です。
医療費控除が受けられる人
医療費控除が発生するのは、その年(1月1日〜12月31日)の間に、自分、もしくは自分と生計を同じにしている配偶者・親族の支払った医療費が一定額を超える場合です。
医療費に含まれるのは、国税庁の医療費控除の対象となる医療費 が詳しく説明していますが、簡単に言うと、
- 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
- 診療等を受けるための通院費、入院の際の部屋代や食事代の費用、医療用器具等の購入代 等
になります。
公共交通機関のを使った通院費も含まれるので、要チェックです。
ちなみに、一年間にかかった市販薬のみの代金で1万2000円を超えた場合には「セルフメディケーション税制」というものが利用できて、この場合にも所得控除ができます(ただし、この記事では関係ないので割愛します)。
一定額を超えたらということですが、一定額というは、
所得合計額が200万円未満の場合は所得合計額の5%
または、
所得合計額が200万円以上の場合は10万円
になります。
なので、家庭で一年間の医療費(助成等を除いた実費)が10万円以上かかっていれば、まず医療費控除ができるということになります(ただし住宅ローン減税等で、既に課税所得がすべて控除されている場合は還付はありません)。
医療費控除が受けられる期間
医療費控除の確定申告は治療等を受けた年の翌年から5年間行うことができます。
例えば、2019年1月1日〜12月31日までの医療費控除の場合、2020年1月1日〜2024年12月31日までの間であれば、いつでも申請することができます。
確定申告は一年のうちでもできる期間が決まっていますが、医療費控除は、確定申告の中でも、払いすぎた税金を返してもらうための「還付申告」に当たるので、いつでも行うことができます。
出産後は医療費控除できる可能性大
【出産とお金】我が家の出産費用 でも書いていますが、正常分娩の出産費用の平均は50万5759円です(正常分娩分の平均的な出産費用について(平成28年度)より)。
出産育児一時金で42万円はもらえるので、実質的に出産にかかる費用の平均は8万5759円です。
また、出産前には妊婦健診もあり、補助券を使っても4〜7万円程度の自己負担が発生します(医療費には保険外診療も含まれます)。
さらに、出産後にはお母さんと赤ちゃんの1ヶ月検診もあり、合わせて1万円程度かかります。
他にも出産前後はいろいろな不調で医者にかかることも多いと思います。
なので、仮に出産が1月1日をまたいでしまったとしても、出産した年は医療費控除ができる可能性がかなり高いです。
医療費控除のやり方
医療費控除は確定申告で行います。
確定申告のやり方はいくつかありますが、普段確定申告をしない人のほうが多いでしょうし、我が家もそうだったので、ここでは普段確定申告をしない人向けのやり方を取り上げたいと思います。
国税庁の 確定申告書等作成コーナー で書類を作成して、印刷した書類を郵送等で税務署に提出するか、e-Taxで送信することで確定申告ができます。
なお確定申告をする際、共働きであれば、基本的に収入が多い人の名前でやったほうがよいです。
というのも、還付金は
控除額 × 所得税率
で計算されるため、基本的に所得税率の高い人、つまり収入の多い人の名前でやったほうがたくさん返ってくる可能性があります。
確定申告書の作成準備
まずは国税庁の 確定申告書等作成コーナー にアクセスします。
私はパソコンでやりましたが、スマートフォンでもできるようです。

はじめての作成であれば「作成開始」を選びます。
入力途中のデータが有る場合には「保存データを利用して作成」を選びます。
次に、提出方法を選びますが、e-Taxを使うにはマイナンバーカードとカードリーダーのセットか、事前の税務署でのID・パスワード発行が必要なので、初めての人は「印刷して提出」を選びます。
すると、推奨環境が表示されるので、必要であればアップデートして、下の「利用規約に同意して次へ」を押します。

事業所得等がない普通のサラリーマン家庭であれば、「所得税」を選びます。

給与・年金以外の所得がなければ「給与・年金の方」の「作成開始」を押します。
次の画面で用意しておくべき書類が列挙されています。
- 所得に関する書類
- 給与所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
- 保険会社から送付される支払証明書 等
- 控除に関する書類
- 医療費・薬剤の領収書
- 生命保険料控除証明書
- 寄附金(ふるさと納税等)の受領証
ふるさと納税でワンストップ特例を申請していた人も、確定申告をする場合には、ここで記入する必要があります。
それと、ここには書いていませんが、
- 還付金を受け取る銀行口座の情報
- 家族のマイナンバー情報
- 申請者のマイナンバーカード、マイナンバー通知カード、または住民票の写し(マイナンバーの記載のあるもの)
も必要になりますので、準備しておくとよいです。
確定申告書の作成
用意しておくべき書類の確認画面で「次へ」押すと、いよいよ入力画面が出てきます。
入力内容が多いので、少し画面の画像を省きながら説明していきます。
●誕生日
確定申告する人の誕生日を入力します。
●所得の種類を選択
「給与のみ」「年金のみ」「給与と年金」の中から選びます。
出産した家庭であれば、「給与のみ」の方がほとんどだと思います。
●勤務先の数と年末調整の有無を選択
勤務先が2つ以上あるかどうかを選択します。
多くの人は1つだと思います。
また、会社で年末調整済みかどうかを選択します。
年末調整が済んでいない場合には、次が所得の入力画面になります。
ここでは年末調整は済んでいるパターンで進めます。
●適用を受ける控除の選択

年末調整済みの場合、年末調整で申請していなくて、ここで申請したい控除を選択します。
ふるさと納税のワンストップ特例を使っていた人も、ここで入力する必要があるので、寄付金控除にチェックを入れます。
私の場合は、年末調整済みだったので医療費控除と寄附金控除にチェックを入れました。
●源泉徴収票の入力
手元の源泉徴収票を見ながら、支払金額等を入力します。
●所得控除の入力

まず医療費の控除から入力しますので、医療費控除の「入力する」を押します。
●医療費控除の選択

今回は医療費控除なので、「医療費控除を適用する」を選びます。
どちらがいいかわからない場合は控除額の試算もできるようになっています。
●医療費控除入力方法の選択

今回はシンプルに領収書から入力する方法でいくので、「医療費の領収書から入力して明細書を作成する」を選びます。
医療費通知がある場合には一番下のものでも良いかもしれません。
●医療費の入力

ここの入力は少し注意が必要で、領収書一枚ごとではなく、医療を受けた人と支払先が同じ領収書ごとに金額を合計して入力します。
例えば、領収書がこんな感じであった場合、
| 日付 | 治療を受けた人 | 治療等を受けた場所 | 名目 | 金額 | |
| ① | 3月17日 | お母さん | ぱぱおクリニック | 診療費 | 1000円 |
| ② | 3月17日 | お母さん | まめお薬局 | 薬代 | 500円 |
| ③ | 4月25日 | お母さん | ぱぱおクリニック | 診療費 | 1000円 |
| ④ | 4月25日 | お母さん | まめを薬局 | 薬代 | 800円 |
| ⑤ | 4月30日 | お母さん | ままお産婦人科 | 診療費 | 5000円 |
| ⑥ | 5月30日 | お母さん | ままお産婦人科 | 診療費 | 6000円 |
| ⑦ | 6月3日 | お父さん | ぱぱおクリニック | 診療費 | 500円 |
| ⑧ | 6月3日 | お父さん | ぱぱおクリニック | 交通費 | 600円 |
合算して入力するのは、治療を受けた人と支払先(治療等を受けた場所)が共通するものなので、
| 治療を受けた人 | 治療等を受けた場所 | 金額 |
| お母さん | ぱぱおクリニック | 2000円 |
| お母さん | まめお薬局 | 1300円 |
| お母さん | ままお産婦人科 | 11000円 |
| お父さん | ぱぱおクリニック | 1100円 |
となります。
通院のための公共交通機関の料金や、やむを得ず使ったタクシーの料金も交通費として医療費控除の対象になります。
なので、例えば「お父さん」の「ぱぱおクリニック」の医療費を入力する場合、
医療を受けた方の氏名 → お父さんの氏名
病院・薬局などの支払い先 → ぱぱおクリニック
医療費の区分 → 「診療・治療」「その他の医療費(通院費など)」
A 支払った医療費の額 → 1100円
Aのうち生命保険等で補填される額 → (あれば記入)
という感じになります。
なので、領収書を、治療を受けた人と支払先(治療等を受けた場所)が共通するものごとに領収書を仕分けしてから入力を始めると合算が楽です。
そして、そのかたまりごとに、上記の入力を繰り返します。
結果、我が家はこんな感じ↓になりました。

入力が済んだら「次へすすむ」を押していくと計算結果の確認画面が表示され、医療費控除額が表示されます。
私の場合は、220330円が控除額でした。
●寄附金控除の入力
私はふるさと納税をしていたので、その入力をしましたが、本題から逸れるので、省略します。
画面の通りに入力していけば、特に難しいことはなくできました。
ふるさと納税は40000円してしたので、控除額は38000円でした。

●所得控除の入力終了
医療費の控除と寄附金控除の入力が済んだので、所得控除の入力画面の「入力終了(次へ)」を押します。
●税額控除等の入力
ここでは特に対象となる寄付はしていないので、入力せずに「入力終了(次へ)」を押します。
●計算結果の確認

還付される金額が表示されます。
私の場合は、13090円でした。
●住民税等に関する事項の入力

給与所得等以外の所得に対する住民税の徴収方法や、扶養親族、別居配偶者についての情報を記入します。
副業等を会社にばれないようにしたい場合には、住民税の徴収方法を「自分で納付」にしておきましょう。
●住所・氏名等入力
申請者の住所、氏名、還付金を受け取る口座の情報を入力します。
●マイナンバーの入力
自分と「住民税等に関する事項の入力」で入力した家族のマイナンバーを求められるので、入力します。
確定申告書の提出
PDFデータをダウンロードした後、自宅でプリントできる人は、それを印刷します。
自宅でプリントできない人は、セブンイレブンのネットプリントやローソン・ファミリーマートのネットワークプリントを利用できるということが書いてあります。
ダウンロードしたPDFファイルをスマートフォンやUSB等の記憶媒体に保存してコンビニに行くことでプリントアウトできます。
プリントアウト後に補完記入・押印が必要
ここで注意が必要で、プリントアウトしたものには押印がされていません。
また追記が必要な部分があることもあります。
「送信・印刷」手順の後の「終了」手順の部分で、記入漏れチェックの項目があるので、忘れずにチェックして追記・押印しましょう。
添付書類
添付書類として、
- 本人確認書類
- マイナンバーカードの表と裏の写し
- (マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、または住民票記載事項証明書) + (運転免許証、パスポート、被保険者証等の写し)
- 寄附した団体等から交付を受けた寄附金の受領証等
- おむつ証明書等
があり、本人確認書類のみ全員必須で、他は該当する控除を申請している人だけが必要になります。
なお、平成29年分の確定申告から、医療費や医薬品購入費の領収書の添付が不要になっているので、それ以前の確定申告をする場合には医療費の領収書の添付が必要になります。
ただし、平成29年分以降の確定申告の場合でも、5年間は領収書を保管しておいて、税務署から求められれば提示できるようにして置かなければなりません。
確定申告書の提出方法
確定申告書の提出方法は
- 管轄税務署へ郵送
- 管轄税務署の受付に持参
- 管轄税務署の時間外収受箱へ投函
です。
ちなみに、自分が住んでいる場所を管轄している税務署は、国税庁のサイト で確認することができます。
医療費控除の還付金はいつ、いくら戻ってくるのか
確定申告(還付申告)による還付金が振り込まれるのは、申請後1ヶ月〜1.5ヶ月後くらいと言われています。
ただし、e-Taxを使った人はもう少し早く振り込まれるようです。
繰り返しになりますが、還付金の額は
控除額 × 所得税率
で計算されます。
自分の所得税率は課税所得の金額によって決まり、
| 課税所得 | 所得税率 |
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超330万円以下 | 10% |
| 330万円超695万円以下 | 20% |
| 695万円超900万円以下 | 23% |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 50% |
という感じになっています。
課税所得は諸々の控除を引いた後の金額になるので年収や手取り金額よりももっと少ないやつです(ここでは細かく説明はしませんが)。
医療費が多ければ多いほど返ってくる金額も多くなりますので、出産前後は医療費控除ができる可能性が高いぞ、というのを頭の片隅に置いておいてください。